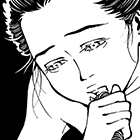江戸時代の商売形態は大きく分けると三つあります。大通りに店を構える大店、町内などで商う小店、商品を担いで売り歩く行商人です。今回は大店での男色事情を見ていきましょう。
大店では身分階級がはっきりしていて、下から順に丁稚・手代・番頭・主人となります。十歳くらいから丁稚としてお店に入り、十七歳~十八歳で手代に昇進、そして一人前と認められる番頭になるのは三十歳くらいでした。
大店の世界は完全に男社会。主人の家族も住居を分けて、嫁や娘もお店に出ることはご法度だったと言われています。そこで男色が行われないはずはありませんよね。
「釜」とは尻のことで、この句の主人公は丁稚の少年です。丁稚奉公といえば、店の誰よりも早く起きて、炊事や掃除を行わなければなりませんが、上司である番頭に身を許せば、そんな仕事は免除され、ぐうぐう寝ていられたというわけです。でも、そんな特権を濫用して、同僚の丁稚に恨まれたりしなかったんでしょうかね?
こちらも夜な夜な番頭に尻を差し出している丁稚の句です。通常の丁稚からすると番頭は怖い存在。しかし、夜の番頭の痴態を知っている丁稚少年からすると、こわもての表情をされてもへっちゃらだったことでしょう。また、番頭の方も、受けの少年の可愛さに、他の丁稚よりも甘やかしていたかもしれません。しかし、時の流れは無残なもの。受けとして可愛がられる期間もそう長くはなかったはずです。初々しかった丁稚少年も成長し、お店に新しい丁稚が入ってきて寵愛を奪われた時、彼はようやく「番頭の怖さ」を思い知ったのではないでしょうか。
現代風に言えば、冴えない中年係長が歓楽街でクダを巻いているといった光景です。順調に出世すれば次は番頭になるはずですが、誰もが番頭になれるわけではありません。お店では出世コースから外れ、店の目ぼしい丁稚は番頭が手をつけている…となると、芳町で遊ぶ(打つ)しかなかったのでしょうね。この手代にも幸あれ、と願うばかりです。
古川柳愛好家。川柳雑誌「現代川柳」所属。